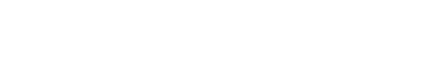インドの農民に深刻な脅威をもたらす気候変動
ジャイディープ・ハルディカール / Jaideep Hardikar(インド)
フリージャーナリスト / 2015年度ALFPフェロー
昼頃吹きはじめた微風は夜に入って激しい嵐になり、やがて雨とともにマンゴー大のヒョウが地面を叩きつけた。雨は24時間以上続いた。
ようやく嵐が収まり、16エーカーの農地を持つ55歳の農民、チャンドラカント・イケ(Chandrakant Ikhe)氏は被害状況を調べはじめた。
「この大惨事のあとの農場を見るには勇気がいったよ」。2015年夏、その2日間にもたらされた未曾有の被害といまだ向き合えずにいる彼は、私にこうこぼした。

サッカーボールほどの大きさに熟れた彼のスイカはヒョウでめちゃめちゃに潰され、見る影もない有り様で畑に散らばっていた。イケ氏の言葉通り「異常なだけでなく、見たこともない」ような状況だった。
私が彼の農場を訪れたのは、異常気象から一週間後のことで、干上がった池の土手とイケ氏の農地との対比があまりに鮮烈だった。夏の真っ盛りだった。本来ならば雨などまったく望めず、地域全域が干ばつに見舞われる時期である。傍らの貯水タンクは空っぽだった。一週間前の豪雨の形跡は残っているのに、水はない。農場はまさに壊滅状態だった。イケ氏は言葉もなく、何が起きたのか理解することすらできずにいた。

もはや食用に適さない無数のスイカの残骸が、辺り一面に散乱していた。被害を受けたのはイケ氏だけではない。彼の村や近隣の数十戸のスイカ農家が甚大な損害に見舞われた。あと一週間ほどでスイカが出荷されれば手にしていたはずの大きな収益は、あえなく指のあいだからすり抜けていった。突然の異常気象がもたらす衝撃だった。繰り返される干ばつで知られ、それさえなければ豊かな地と考えられているマハラシュトラ州マラトワダ地方の村での出来事だった。
突然の害を被ったイケ氏のケースは特殊でもなければ、珍しいことでもない。来る年も来る年も、急激に変わる気候に苦しむインドの農村では、このような話は枚挙にいとまがない。
ムンバイから800マイルほどのところに位置するマラトワダは、もともと雨の少ない地域である。イケ氏の住む辺りは夏の盛りが近づくと乾燥し、スイカは地面に掘った井戸からの地下水で育っていた。順調にいけばおよそ200万ルピー(35,000ドル強)の収入が期待できたところを、2日間で全てが無になった。
これが異常降雨の姿だが、もう一つ別の例を挙げよう。何マイルも離れたインド南部の一角にはタミル・ナードゥ州のカーヴィリ川デルタ地帯がある。かつては栄えた地域だった。
2017年の夏、私はからからに干上がったこのデルタ地帯を旅していた。この地方は数十年前までは豊かな水田と野菜栽培で知られ、「南のガンジス」と呼ばれるカーヴィリ川流域には文明が栄えていた。ところがそこを旅しながら、私は前代未聞の文明逆行プロセスを目撃しているのではないかと思わざるを得なかった。
人々は水と仕事を求めて流域の村々から移住していた。数千の農民が水を渇望していたが、どこにも見当たらない。干からびて枯渇したカーヴィリ川とその無数の支流、そして過去2000年のあいだ王たちがデルタに築きあげた数万の運河や湖からは、水田、サトウキビ、野菜、果樹園、魚など、ありとあらゆるものが消えてしまっていた。現在この地方全域で干ばつと深刻な水不足が繰り返されている。
ここ数十年、カーヴィリ川デルタで着実に進みつつあった気候変動に対処する準備がなかったがゆえに加速した人災は、今や極めて重大な問題を引き起こしている。2016~17年の農業シーズンには100人以上の農民が借金の泥沼にはまって自殺し、数十人が医者が言うところのショック死で命を落とした。膨大な損害によるショックとストレスに起因する突然の心臓発作だった。
インドの小作農が危機に瀕してもう20年になる。この危機はいろいろな要因が組み合わさって起きた。とりわけ、突然かつ極端な異常気象と、それに対する政府レベルと地域レベルでの完全なる準備不足については、疑いようがない。毎年のように起きる異常気象でインドの小作農がどのくらい打撃を受けているのか、私たちはそれを理解することも、数量化することもできていない。
しかし、気温の上昇やモンスーンパターンの劇的な変化に伴い、インドの農業が影響を受けるであろうという兆候や研究については、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)からインド気象局やインド熱帯気象研究所によるものまで、多数ある。
マハラシュトラ州プネーにあるインド熱帯気象研究所の研究によれば、インドの総雨量のほぼ70%をもたらす南西モンスーンによる降雨が、インド全土で4.7%減ったことが確認されている。異常豪雨(一日当り降雨量10㎝以上)の頻度と強度が増し、通常降雨の頻度が減っている。同研究所の2009年8月の報告では、同地方にある165地点での一日の降雨量データを観測して雨量極値(24時間最高降雨量)を確かめ、過去40年にそうした現象の頻度と強度が変わったかどうかを調べた。その結果、1960年以降、豪雨の頻度がかなり増え、その強度も急激に増していることが分かった。さらに大都市、避暑高地、島嶼部で豪雨被害が起きていることも分かった。
またパデュー大学(米インディアナ州)の2009年の調査では、今世紀末にはインドの夏のモンスーンが大幅に弱まる可能性があると報告されている。
デリーにあるインド工科大学の大気科学センターでも同様の傾向が報告されている。この研究では、1951年から2004年までの降雨データを分析し、過去50年間に長期降雨期間(一日の降雨量2.5㎜以上、連続4日以上の降雨)が減り、短期降雨および乾燥期間(一日の降雨量2.5㎜以下、降雨継続期間一日前後)が増えたとされている。
インド農業は6割以上が雨に頼り、農民の8割近くが零細・小規模農家である。つまり5億人近い人々がモンスーン頼みで、土地からの収穫によってかろうじて生活をやりくりしている。インドのモンスーンは動的システムだ。それ故そのシステムが崩れ、確実性を失い、気まぐれ男のようにふるまうと、対抗する準備ができていないかぎり、確実に壊滅の「レシピ」になる。
100年以上の降雨データを研究したインド工科大学マドラス校は、より短期間で同じ降雨量が観測されていると報告している。豪雨は作物や降水の地中浸透に影響を及ぼす。水ストレス(水需要の逼迫)のある地方では地下水の過剰使用が警戒域に達している。
いろいろな意味でインド農業は、変動する気候の中で新たに常態化しつつある事象によって深刻化している対照的な状態の間を行き来している。つまり今日のインドにおいて、干ばつと洪水が密接に関連しているのだ。
2013年のことだ。インドの広大な国土は干ばつに見舞われた。農業が被害を受け、極端に少ない雨量と地下水の過剰使用により地下水が枯渇し、使えなくなった。干ばつと深刻な水不足でインドの三分の一が被災したと公式にはいうが、この期間に説明のつかぬ突然の極端な異常気象で夏の収穫が損害を受けた地方もあるという。
同じ地域が極端な豪雨と干ばつを同時に経験することもある。2016~17年にインド西部および南部で私が目撃し、詳しく報告したように、インドの河川は干上がり、三大河川(ゴーダーヴァリ川、クリシュナ川、カーヴィリ川)は水源から枯渇した。
これが地方経済にもたらした影響は前代未聞の規模だ。昨年、農業に関する常任委員会から議会に提出された報告には、この国の農業に関して切迫した懸念がいくつか述べられている。それによると、気候変動は種子システム、土壌、水利、生産過程など農業のほぼあらゆる局面に影響を及ぼしている。それが収入に悪影響を与え、農民を貧困に追い込んでいる。
気候の大まかなパターンは分かっているが、いまだに分からないのは地域によってその影響にどのようなばらつきがあるかだ。この点で、インドの各州は一役買っている。
2015年、7月の異常豪雨でインド中部では3,000kmに及ぶ道路が寸断され、300余りの中小の橋が流され、1万軒の家屋を破壊、150万ヘクタールの土地に生育中の作物が壊滅、さらに数百数千ヘクタールの土地の作物に損害を与えた。洪水のほか落雷でそれぞれ100人以上が亡くなり、被害のあった時期には200人近い農民が自殺した。
インド農務省は、地球温暖化で今世紀中に作物生産量が最大40%減少するおそれがあると警鐘を鳴らし、また政府の経済調査は、すでに乏しい農民の収入が25%減少すると見ている。これが意味するのは、残念ながらインドのような国々では、農民や沿岸部の村落のような弱い地域は生態循環の機能にほぼ完全に依存しているため、一掃されてしまうということだ。
では、答えはどこにあるのか。国家の政策は重要だが、この問題の解決の一部は、影響を受ける側のコミュニティからやってくる。インド全土では伝統的種子保存運動が活発化している。伝統的種子を守る農民がネットワークをつくり、作付様式に変化をもたらし、変化とそれに対する適応の学習を含む多様な策をめぐらしている。こうした動きは小規模でばらばらだが、重要だ。なぜなら、こうしたものは遥かに弾力性があるからだ。
こんな例がある。マハラシュトラ州東部のバンダーラ地区は零細または小規模の稲作農家が多いが、零細農家が集まって16種ほどの地域在来種を特定した。これらの種子は短期・長期的にモンスーン気候変動に対して耐久性と抵抗力に優れている。
インド全土でこうした農民によるグループが多数生まれている。気候変動の影響に対応するため、急成長していると言ってよい。ただ、このようなグループについては今のところ研究されておらず、その策は認知されていない。
地元農民の知恵や、自然適応力のある作物や在来種への観察が、気候変動の中で農場システムの維持にとって重要であることを、この新たな集団的努力は教えてくれる。何十ものこうした現場経験が示すのは、新しいアプローチが必要とされているということだ。それは近代の科学知識の上に築かれたものであると同時に、草の根の熟練者による不屈の知恵から生まれるアプローチだ。その担い手は市場や異常気象からの攻撃と闘う小作農たちである。
※本記事の内容や意見は著者個人の見解です。