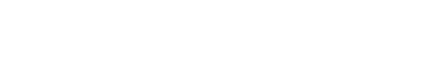民主主義の《民》を問う
グナワン・モハマド / Goenawan Mohamad(インドネシア)
エッセイスト / 劇作家 /「Tempo」誌 創始者 / 1997年度ALFPフェロー
今日民主主義は、半分忘れられかけたラブレターにたとえられるかもしれない。ありし日のラブレターに綴られた、真率で心温まる会話に焦がれた情熱——しかしそれは、時が経つにつれ薄らいでしまった。民主主義もまた、言葉としても実践としても、当初の初々しさはもう見られない。それでも民主主義は、今は混迷を深めてはいても、いつか再びはつらつとした生命を蘇らせてくれるのではないかと思わせる弾力を失ってはいない。
インドネシアの民主主義は、まさにこのラブレターの物語だ。1998年の《改革》によって、スハルトの独裁的支配は終わりを告げ、国内には変革を称える声が満ちあふれた。これでもう大企業は大統領一族によって独占されなくなる。市民生活が軍部によって統制され嫌な思いをすることも、逮捕されて無期限に拘束されることもなくなる。政党が自由に立ち上げられ、権力の集中は排除され、指導者は、大統領から県知事に至るまで、選挙によって選ばれ、いつまでも居座ることはできなくなるだろう、と。
しかし現実には、すべての旧弊は今日まで生き残っている。スハルトの「新秩序体制」の終焉とともに、人々は、宗教、思想、生活様式について、個人の自由を守ってくれる制度が施行されるだろうと期待したのだが、蓋を開けてみれば、新しい理念が導入されるわけでもなければ、政治家たちが本気を見せたわけでもなかった。今日のインドネシアの司法は、相も変わらず、政治家の口利きや、収賄や、判事たちの「思想信条」によって左右されている。警察からして賄賂がまかり通っている。
インドネシアは、激動の「アラブの春」の余波に揺れる中東諸国に比べれば、暮らし向きはまだ良いほうだし、ロシアや中国のように、再び独裁政治に退行しているわけではない。けれどもその民主主義は見かけ倒しにすぎず、実態は、政党は少数のボスに牛耳られ、選挙では賄賂が横行し、議会は権限を肥大化させ責任追及を免れている。
インドネシアの政治的空気を一言で言うならば、気抜けである。
この惰性的沈滞に活を入れることはできるのだろうか。それは世界にとっても重要な問いである。というのは、世界のほとんどの民主主義国家にも同じ病が忍び込みつつあるからだ。フランシス・フクヤマは冷戦の終わりにあたり、「リベラル・デモクラシー」の最終的な勝利宣言をしたが、人々は今やすっかり醒めた目で、民主主義は必要悪にすぎない、いやそれどころか歴史的な大過失だとさえ言い始めている。フクヤマ自身、2017年には、民主主義が後退することなど予期していなかったと認め、どうしてそんなことが起こりうるのか、理論的に説明できないと言っている。確かに民主主義は多くの良いものをもたらしてくれる。人々の行く手に希望を示してくれるものだ。しかし他方では、人々の不満を醸成しやすいということも否定し難い。フクヤマは、今そのことを知ったのだ。
本年「エコノミスト」誌が行った、60の指標を用いて民主主義の成熟度を計測するリサーチによると、世界の中で「成熟した民主主義社会」に住んでいる人々は、5%以下である。そして167カ国中89カ国が、昨年よりスコアを下げている。つまり民主主義は退潮過程にあるということを示唆している。
紀元前5世紀の古代ギリシャで、ソクラテスが民主主義に対し表明した懸念が、歴史的に回帰し、現代のわれわれに取り憑いたような感がある。民主主義 (democracy) の主体である《民》(demos) に、はたして良き共和国をつくることができるのだろうか? 周知のようにソクラテスは、航海のアナロジーによって議論を進める——「もし君が航海に出るとしたら、誰に船長になってもらいたいと思うだろうね? 誰でもいいと思うだろうか、それとも航海にどんなことが求められ、いつ何をしなくてはならないかを訓練によって熟知している人がいいと思うだろうか?」ソクラテスは、国政は《民》には任せられないと考えていた。しかしそれは自明のことと思ったのだろうか、それ以上議論を掘り下げることはしていない。
《民》は、歴史の中でその意味内容を変えてきた概念である。換言すれば、特定の時と場所に付随する事象だということになる。人々が通りを占拠し、スローガンを叫ぶとき、ジャック・ランシエールの言葉を使えば、彼らはその時代の「《民》の像」となっている。18世紀のフランスでは、《民》の主体は、貴族階級と教会に抑えつけられていたブルジョワ階級であった。そして彼らが社会の中で組織化され、フランス革命の原動力となったのである。
一方20世紀の中国では、《民》は小作農であった。彼らは鍬しか生産手段を持たない極貧階級であったが、奇妙にも「プロレタリアート」という範疇に溶かし込まれた。毛沢東の中国共産党にあっては、プロレタリアートが《民》を率いるというのが絶対的教条であった。
つまり《民》とは、時と場所に応じて、公正と平等(ないし自由とつがった平等)を要求することで、存在感を現してくる集団であり、その集団を、政治史において《民》と呼んだのである。歴史を変えるのは革命ばかりではない。交渉、暫定的な合意によって歴史が動いていく時代もある。18世紀以降、世界の多くの地域における《民》は、投票を行う市民という姿を取る。19世紀以降の社会は、ヘーゲルの表現を借りれば、「人々の欲求のシステム化」の過程であり、21世紀の《民》は、資本主義パラダイムの下での「政治的消費者」となっている。今日の《民》は、個人的な欲求と欠乏感を抱えながら、ほとんどの時間を自己中心的な世界に閉じこもって生きている人間たちとして捉えることができる。
《民》という言葉は、その定義が一意的に定まるものではないがゆえに、変動著しいわれわれの時代にはとくに、当座使える呼び名として、やや場当たり的に用いることしかできない。消費者としての《民》は、自分の意思で動いているように思われるかもしれないが、実はそうではない。消費者は神様だという神話はまやかしでしかない。われわれは香水を買うとき、ラベルや広告に支配されて買っている。同様に、選挙権を持った消費者の多くは、権力の繰り出す政治キャン ペーンに動かされて投票している。
つい最近、Facebookを通して集められたわれわれの個人的データが集積され膨大な情報バンク(ビッグ・データ)が形成されているということが報じられた。目的は投票者の好みを抽出し、民心操作に使うためである。フーコーの言う「ディスコースのテクノロジー」の典型とも言えよう。こうなると有権者/消費者は、言葉を発することはできても、社会に対する有意性を欠いた会話しかしない存在に堕してしまう。
代表 (representation) という概念も怪しくなってくる。民衆の意思を制度的に代表することは、いつも遅れて行われる。民衆の欲求の最初の表出と、それに対する方策や政策の制定には時間的なズレが生じざるを得ない。加えて、ドゥルーズの言葉に「代表 (representation) は表出 (presentation) を前提とする」というのがあるが、そもそも《民》の意思が表出されていないのであれば、「代表は意味を失う」ことになる。
時間的なズレもあれば空間的なズレもある。とくにインドネシアのような広域に及ぶ多島国においては、《民》の存在する場所・社会的背景と、その代表者たちのそれとの間には大変な距離が存在していて、議論の焦点がしばしば民意から逸れてしまう。とどのつまりは、政治過程のある段階において、民衆は自分たちの意思が無視されていると感じるようになる。
《民》と為政者たちの離間によって、政治討論の理論的根拠は崩れ去った。いわゆる「理性の穏健な声」を耳にすることが次第にまれになりつつある。その結果、議会の外での紛争が生じかねない。その危険性はインドネシアの政治の歴史にいつも潜在している。スカルノの「指導制民主主義」(1958~1966)、スハルトの「新秩序体制」(1966~1998) の両方の時期において、専制的ないし官僚的な紛争管理がなされているが、それは立憲民主主義の短い実験 (1945~1958) の後の議会に対する幻滅の産物といえよう。
現状の政治体制では、民衆が、国家との一体感(ないし対決)を求める声を挙げたり、自分たちの意思の実現を求めて再起したりする可能性を無視できない。いわゆるポピュリスト政治家の魅力はリアルである。ポピュリズム的独裁は、街頭での大々的な示威行為によって、議会においても司法においても、審議による意思決定を無力化しようとする。
理性的な議論による政治という神話は、その因果な報いを迎えることになる。すなわち、《民》の統合という神話である。後者は前者の拒絶によって結束を図る。2018年のジャカルタ市長選挙が好例である。敬虔なクリスチャンで、ジャカルタ市政ですぐれた業績を挙げ、高い尊敬を受けていた現職の市長は、彼を貶める民族主義的、宗教的な捏造情報の流布によって、選挙に敗れてしまった。彼が抗弁に打って出ると、大多数の宗教であるイスラム教に対する侮蔑だとして喧伝され、ついには投獄されてしまった。
2019年の大統領選挙に向けての選挙運動がすでに始まる中で、インドネシアは過去のポピュリズムの記憶を甦らせた。この選挙でもまた頑迷さの嵐が吹き荒れることになるのだろうか。加えて、誰が当選しようがどこが勝とうが、不可避的に金のかかる行事である選挙が、再び少数の独裁的政治家たちによる闘争の場になるのではないかという払拭し難い懸念がある。民主主義的プロセス(ないし闘争)は、決して民衆を幸福にしないし、約束の地に導いてくれない、それが民主主義の悲しい宿命なのではなかろうか、という思いに駆られてしまう。
政治に失望はつきものだ。政治とは、諸党派がしのぎを削りながら、自由と公正を目指す未完のプロジェクトである。しかし、半分忘れられているだけにすぎない、《民》の、《民》による、《民》のためのラブレターを新たに蘇らせることができれば、政治は有効に機能し、生き生きとした意味のあるものとなっていくに違いない。
※本記事の内容や意見は著者個人の見解です。