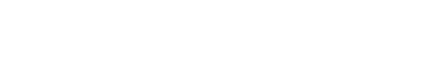ある映画のある瞬間
マリアン・パストール・ロセス / Marian Pastor Roces(フィリピン)
芸術批評家 / キュレーター / TAO Inc. 代表 / 2003年度ALFPフェロー
フィリピンが歴史的岐路に立つ今、芸術制作と社会の結びつきを説明する上で、1本の映画に焦点を当てたい。
この作品は、今日の業界用語でいうところのインディーズ映画だ。20代や30代の人々が制作や監督、俳優として関わり、中には主演を務めた子役も含まれている。2018年シネマラヤ映画祭への出品を目指してつくられた、低予算映画である。シネマラヤはフィリピン文化センター(CCP)が10年ほど前から毎年開催する映画祭で、商業的な興行網ではなかなか配給されない若くて先鋭的で低予算なプロジェクトを対象としている。シネマラヤそのものが、フィリピン芸術界が卓越した若い力へと順調に舵を切っていることの証しである。さらに、『リーウェイ』というインディーズ映画では、シネマラヤの特異性が放たれた。『リーウェイ』は、言うなれば歴史上の古傷にメスを入れることで深刻な「炎症」を和らげる作品だった。
この映画について説明するが、それは賛辞を重ねるためではない。5年ほど前からフィリピンで幅を利かせている歴史修正主義に芸術が打ち勝った瞬間として、この映画を認識し、かみしめるためだ。また本作品は、芸術こそが歴史修正主義を打破できる唯一の手段ではないかという抽象的な発想に確かな実感を与えてくれるものでもある。
『リーウェイ』というタイトルは、この物語の中心人物で、フェルディナンド・マルコスによる軍事独裁政権の最後の数年間に当たる1980年代前半に左派ゲリラを指揮した女性司令官の字名から来ている。忘れられない出来事が多々ある中で、この映画は、激戦で親しかった同志を失い、自らも捕虜となる身重の軍人リーウェイ司令官に焦点を当てている。彼女は、やはり反政府ゲリラの戦闘員である夫とともに、軍事施設に収容される。夫婦はほかの政治犯たちに囲まれながら、その施設で次男を生み育てる。ダキップ(タガログ語で「捕える」の意)と名付けられたこの息子に、刹那の「想像ごっこ」を通じて希望というものを伝えるリーウェイと、我が子に絶望とは何かを理解させたい夫。二人の間に緊張が生じる中、物語は展開する。夫婦は施設で三人目の子となる娘を授かるが、やがてマルコス政権の崩壊で一家が釈放されたとき、次男のダキップは10歳になろうとしていた。ついに自由になったダキップは、明らかにリーウェイの想像力を受け継いでいた。
試写会では、エンディングで「この映画の制作費の一部には、マルコス元大統領に対する人権侵害訴訟でリーウェイとその家族に支払われた賠償金が使われている」という字幕が現れると、会場は熱気に包まれた。そして、最後にこの新人監督がかつてのダキップ少年であること、さらに、今はキップと呼ばれるその青年が確かに母親の限りない好奇心を受け継いでいることがわかると、観客は歓喜に沸き返った。「マルコス、ヒトラー、独裁者、アメリカの犬」という、1970年代の街頭集会の定番シュプレヒコールが2,000席を擁するCCPの劇場を満たし、オーケストラピットから上階のボックス席、さらには1969年にマルコスの妻イメルダ夫人からの要請でつくられた巨大な建物全体に響き渡った。
実際、試写会が行われた建物は、1970年代以来マルコスの野心の象徴だった。CCPは1986年のエドゥサ革命以降その運営を担当し、ポスト戒厳令期の政治的な展開に合わせて自らの使命を見直してきた。本稿では現在のCCPの方針や事業について十分に論じることができないが、CCPが今日シネマラヤ映画祭を通じてこの国の芸術分野に極めて大きな貢献をしていることは間違いない。
だが、古びたCCPの劇場で「再び独裁を許すな!」の大合唱を経験するのは、まったく別の話だ。その場にいた数千の人々にとって、この叫びはカタルシス、つまり日常の抑圧された感情を解放させるものだった。異議を唱える声が――少なくとも想像の世界において――洞窟のような赤い劇場から沸き上がり、逮捕に抵抗したとされる麻薬常習容疑者らを次々に葬り去る新たな独裁者に支配された今日のフィリピンへと流れ出たのだ。死刑制度のないこの国で、現職の大統領による「麻薬撲滅戦争」の名のもとに27,000人が殺害されている。明らかに、独裁支配への抵抗を抑え込もうとする恐怖政治だ。この21世紀の独裁者の誕生を可能にした大きな要因は、マルコスが略奪した財産と、権力への復帰を狙うマルコスの子どもたちの企みだった。彼らは歴史の修正という目論みのためにソーシャルメディアを駆使し、衝撃的なまでの成功を収めたのだった。
彼らの巧妙なメッセージは、ターゲットである若者をいわば催眠状態に陥れ、戒厳令期は文化・経済の黄金期であり、マルコスは政治活動家の拷問や殺害とは無関係の慈悲深いリーダーだったという解釈へと誘導する。共産主義者による抵抗は、20世紀半ばのマルコス独裁時代にピークを迎えた。リーウェイの家族のような貧しい人々が、武力による革命こそが権力の一極集中によってもたらされた極度の社会的不平等への正しい対処法だと信じていたのもその頃だ。1986年、マルコス一族とその支持者たちは、数十年にわたる抵抗を凝縮したような4日間にわたる反独裁の大きなうねりによって排除された。あの当時は陶酔感に浸りながら、この国はいかなる独裁的野望からも守られるような気がしていた。われわれはあまりにナイーブだったのだ。
『リーウェイ』の試写会に行くまでは、昨今におけるマルコス時代の史実の歪曲はどうしようもないものだと思っていた。ファクトチェックやメディアリテラシー向上のための「軍資金」がなければ、戒厳令に関するバラ色の記憶は作り続けられる。この虚偽に満ちた空気の中で、大虐殺と前代未聞の腐敗は常態化し、やがて人々の間で受け入れられるようになる。試写会の中で、『リーウェイ』は今日の複雑な欺瞞の構造を一瞬とはいえ切り裂いた。この映画は若く、その作り手たちもやがてより高度な技術を身につけていくだろう。しかし評論家が何と言うかは問題ではない。『リーウェイ』の物語は真の教育を通じて時代を超えたのである。
※本記事の内容や意見は著者個人の見解です。